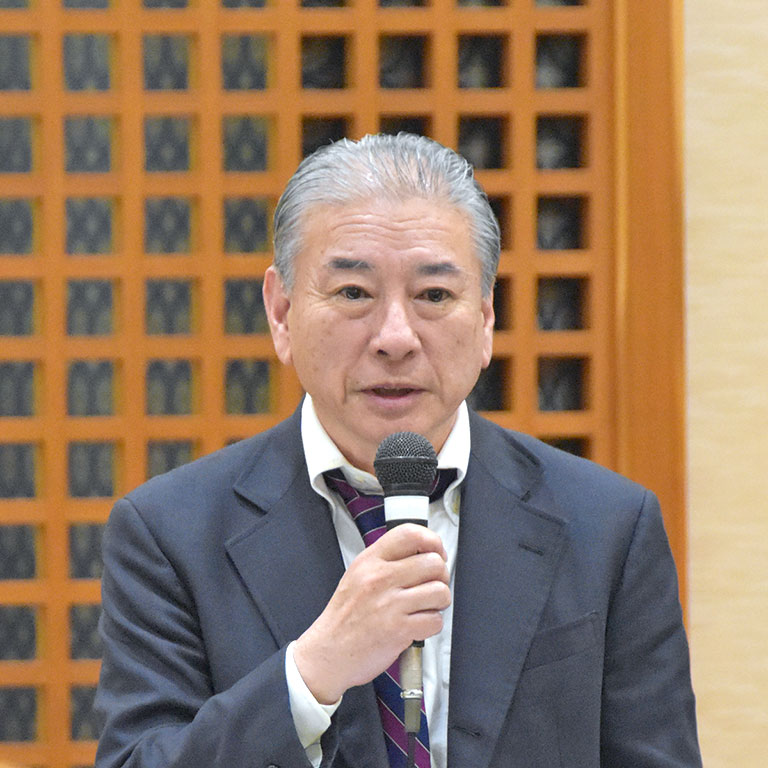石川 多歌司 選
2025(令和7)年
大阪の芭蕉忌
兼題句
八十路なほ夢追ひかけて秋高し(神戸市)上岡 あきら

平均寿命は益々伸び傘寿になっても尚夢を追いかけている作者。誠におめでたい限りである。傘寿ともなると腰痛とか膝の痛みで悩む人や糖尿病等で病院通いの人が多くなり闘病生活の方が増えるが、作者は息災で夢を追う程頭脳も衰えていない。夢はいろいろあるが、俳句の更なる探究もその一つであろう。それに相応しい季節の天高しである。
杖曳いて終となるやも親鸞忌(甲賀市)清野 光代

高齢になると身体の何処かが悪くなる人が多い。殊に足の具合が悪くなる人が目立ち日常生活に杖に頼る人が多くなる。作者も今年は杖に頼りながらも親鸞忌の法要にお参りすることが出来たが、この足の調子では今年が最後となるかも知れないと不安の募る作者。適度のリハビリをしてそれ以上悪くならないように祈るばかり。どうかお大事にして下さい。
生かさるる限りこの道翁の忌(甲賀市)清野 光代

高齢の作者なのであろう。今日までの息災に感謝をしつつ、これも俳句のお蔭と思っている作者。人間の寿命など誰も分からないが、生きている限り今やっている俳句の道をひたすら進む積りで芭蕉忌に際して決意を新たにする作者の気概が伝わってくる。俳句は奥が深く日頃の研鑽が大切であります。向後の変わらぬご精進をお祈りします。
席題句
現在校正中です。