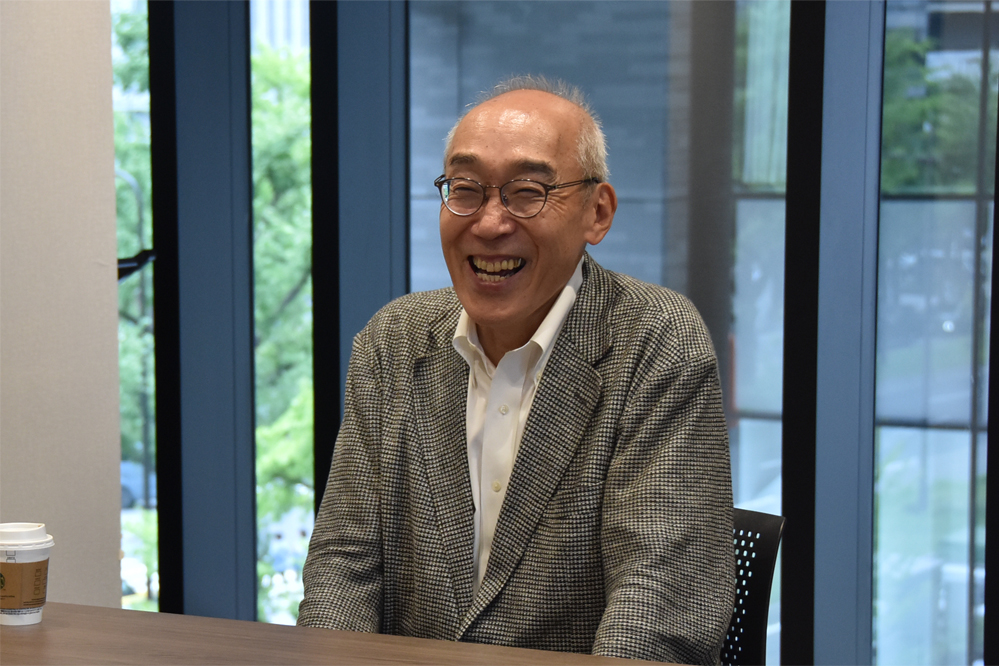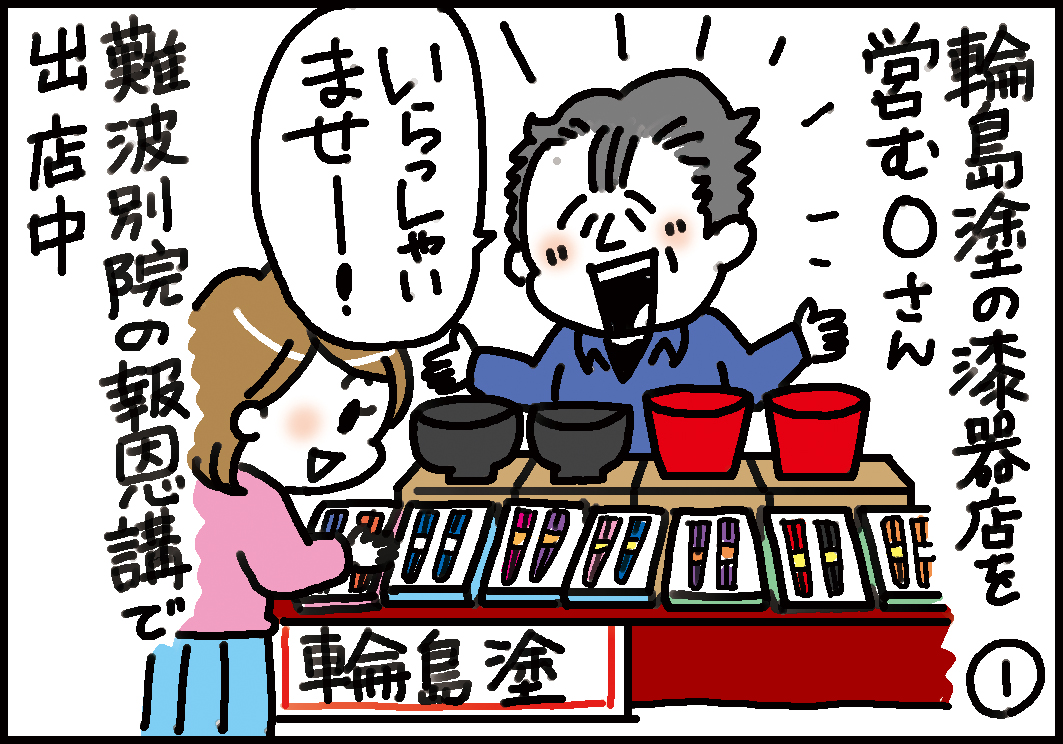「『蔦重』こと蔦屋重三郎の”粋”な生き方をたずねて」この人にきく・車浮代さん②
浮世絵との出会いをきっかけに、江戸文化に魅了された車浮代さん。5月号では、江戸時代の食文化を中心に話を伺いました。
6月号では、大河ドラマで話題の「蔦重」こと蔦屋重三郎の生き方について尋ねてみたいと思います。
〈前半はこちら〉

くるま・うきよ/1964年大阪生まれ。大阪芸術大学卒業。江戸文化、特に浮世絵と江戸料理に造詣が深い。著作は30冊に及び、『蔦重の教え』(飛鳥新社/双葉文庫)は累計7万部を超えるロングセラーとなる。
日々の感謝と未来への希望
江戸時代後期に輝かしい足跡を残した出版プロデューサー、蔦屋重三郎。さまざまな書籍や浮世絵の世界に革命を起こし、後世に名をはせる数々の才能を見出した功績は、今日においても色あせていません。
「浮世絵を紐解くと、必ずその名前に突き当たりました。何しろ、浮世絵界の四大巨頭のうち三人に関わっている。それも、歌麿と写楽を世に出したなんて、本当にすごい人なのに、なぜこんなにも一般には知られていないんだろうと強く感じていました」と、浮代さんは蔦重との出会いを振り返ります。
その功績と知名度のギャップに惹かれた浮代さんは、蔦重の生き方や思想を深く掘り下げ、『蔦重の教え』(飛鳥新社/双葉文庫)として一冊の小説にまとめました。サラリーマンの主人公が、江戸時代にタイムスリップして蔦重に助けられ、その生き様に惹かれていくというユニークな物語は、ロングセラーとなり、多くの読者にその魅力を伝えています。
浮代さんが蔦重の生き方の中で特に大切にしているのが、「今日様」と「お陰様」という二つの言葉です。「彼が日常の中で大事にしていたであろうこの言葉は、日々の感謝の念と、未来への希望をつなぐ大切な思いです」と語りました。
「『お陰様』に感謝するということは、目の前にいる人だけでなく、その人を形成した親や先祖、そしてこの世界に存在するすべてのもの、陰ながら私を支えてくださっているものに感謝するということです。水や火、空気といった、私たちが生きる上で欠かせないものへの感謝も含まれます。一方、『今日様』に感謝するというのは、この瞬間から始まる未来、これから先の時間に感謝するということなんです。何かに成功した時だけでなく、これから起こるであろうすべての可能性に感謝することで、日々の生を精一杯生きようとする姿勢が生まれるのだと思います」
粋がらないとこが「粋」
もし現代に蔦重が生きていたなら、間違いなく時代の寵児となっただろう、と浮代さんは言います。「彼は、売れない絵師の才能を見抜き、斬新な企画で次々とベストセラーを生み出した、まさに時代を先読みする天才的なプロデューサーでした」。その先見の明と革新的なアイデアは、現代においても十分に通用するでしょう。
さらに、浮代さんは蔦重の人物像から「粋」という日本の美意識についても語ります。「『粋がらないところが粋』だと思うんです。見栄を張ったり、格好つけたりするのではなく、ありのままの自然体で道を切り拓いていく。そこに、蔦重の真の魅力があるのではないでしょうか」。吉原という遊郭に生まれ育ち、困難を乗り越えて、出版界の頂点に立った蔦重の生き様は、まさに「粋」そのものだったと語ります。
「今日様とお陰様」の精神、時代を先導するプロデュース能力、そして飾らない生き方という「粋」。これらは、蔦屋重三郎という唯一無二の人物を通して、現代を生きる私たちに示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
(2025.06.01 南御堂新聞 第755号掲載)