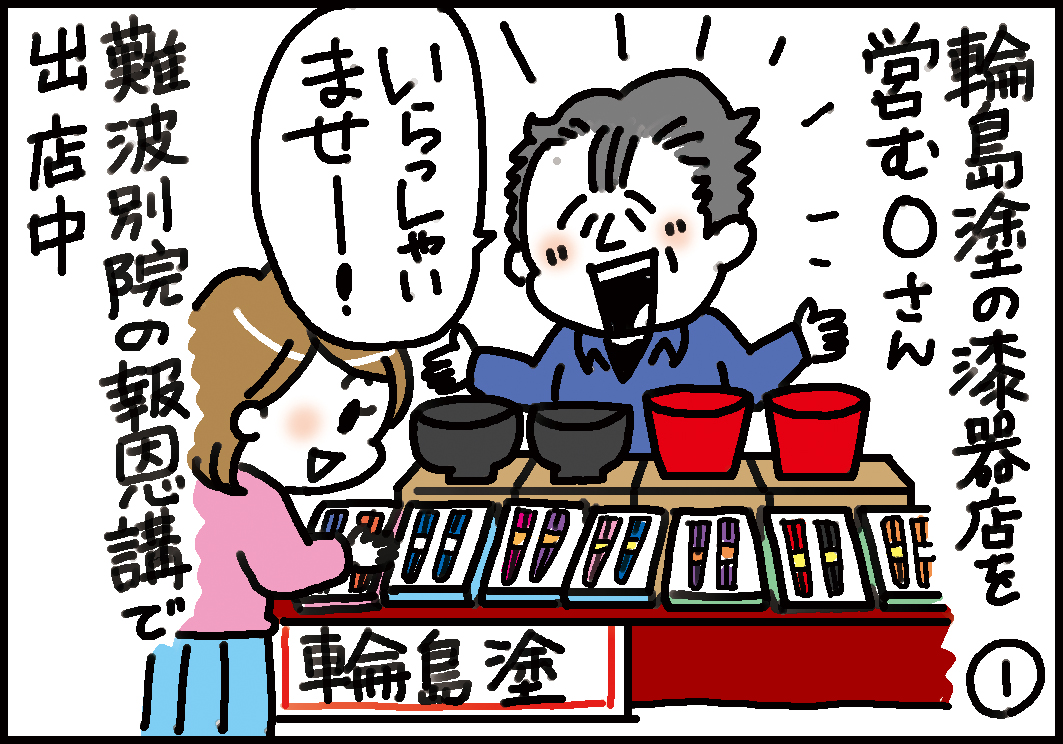「“共創価値”生み出す取り組み」この人にきく・尾中友哉さん②
手話を母語に育ち、家庭と社会のあいだにある言語やコミュニケーションの違いと向き合ってきた尾中友哉さん。
かつて手話が否定された時代を生きた両親の経験も原点となり、今は聞こえる・聞こえないの境界を越えて「共創価値」を生み出す取り組みを、教育や研修の現場で実践しています。

おなか・ともや/1989年滋賀県生まれ。認定NPO法人Silent Voice代表理事。ろう者の両親のもとに生まれた聞こえる子ども(コーダ)として、母語として手話を身につける。平成30年間の家庭内の生活変化の大きさと社会の変化の小ささに疑問を持ち、Silent Voiceを創業。2018年人間力大賞・内閣総理大臣奨励賞受賞。映画『ヒゲの校長』では主人公高橋潔役を演じた。。
父らしく、母らしく
今でこそ一つの言語として認識されつつある手話にも、「冬の時代」があったといいます。かつては「手話を使うと発音が上達しない」と考えられ、教育現場では声を出して話す訓練(=口話法)が重視されました。
手話は学習を妨げるものとされ、使用を禁じられることもあったのです。尾中さんの両親も、その時代を生きた世代です。
そのため、父方の祖父母は手話ができず、幼い尾中さんは家族間の通訳を担いました。
やがて大人になった尾中さんは、ある日ふとした折に、両親へ「聞こえるようになりたいと思ったことはある?」と尋ねたことがあったといいます。父は迷わず「なりたい」と答えました。職場で声が届かず、名前を呼ばれても気づけない父に向かってネジが投げられたこともあった——そんな経験が、その答えににじんでいたのです。
一方で、カフェを切り盛りしていた母は、「家族とお客さんがいて幸せ。自分を変えようとは思わない」と穏やかに答えたといいます。手話を否定された時代を生きながらも、自らの言語を大切にしてきた母らしい言葉でした。
「父と母、どちらが正しいということではなく、それぞれ歩んできた人生がそのまま表れている」。尾中さんはそう語ります。その言葉には、聞こえる・聞こえないという線引きではなく、一人ひとりの選択を尊重する姿勢がありました。
“ラーメン”は伝わる?
今、教育や司法でも手話が見直されつつありますが、学べる場はまだ少ないそうです。
「耳の聞こえない子どもたちは、全国のどこに生まれるか分からないので、自然と点在している」と尾中さんは話します。
教育現場の現状についても、例えば、滋賀県のろう学校は草津に1校だけで、遠方からの通学は現実的ではなく、常に付き添うことのできない共働き家庭ではなおさら難しいのです。
さらに、聞こえにくい子どもは周囲から気づかれにくく、「自覚がないまま“聞こえる人の世界”で頑張り続けてしまうこともある」といいます。地域に散らばり、ろう学校にも通えず、見えにくい存在になってしまう子どもたち。こうした現状こそが、尾中さんが支援に取り組む理由になっています。
サイレントボイスの企業向けコミュニケーション研修では、参加者はまず“声を出さない・文字を書かない”というルールのもと、身ぶりと表情だけで意思を伝えるワークに挑みます。普段、言葉に頼っている参加者にとっては、最初の数分で混乱が広がるのだとか。例えば、好きな食べ物「ラーメン」を伝えるだけでも、麺をすするジェスチャーをすると「うどん?」と思われてしまったり、“なると”を表しても最近は入っていないことが多く、相手にうまく伝わらなかったりと、やり取りが何度も行き違います。
そこへ、ろう者の講師が入り、相手の視線を捉え、表情の変化を読み取りながら、伝わりやすい動作へと導いていきます。聞こえない人にとっては、音に頼らずに相手の意図を読み取ることは日常のコミュニケーションそのもの。参加者は、日常の中で身につけてきたその伝え方に、驚かされるといいます。
尾中さんは、「“聴覚障害者”に対して劣った存在、助けられる存在という思い込みがどこかある」といいますが、研修の終盤には、無意識に抱いていたその優劣の意識が解け「先生、どう伝えたらよいですか」と講師に助言を求める姿も見られるといいます。
視点を変えて「違い」に向き合えば価値が生まれる。尾中さんはそれを「共創価値」と呼び、その視点をどう社会に根づかせていくのかが、これからの課題といいます。〈終〉
(2025.12.01南御堂新聞 第761号掲載)
聴覚障害のある子どもたちの応援はサイレントボイスのWEBサイトから
https://silentvoice.org/donate