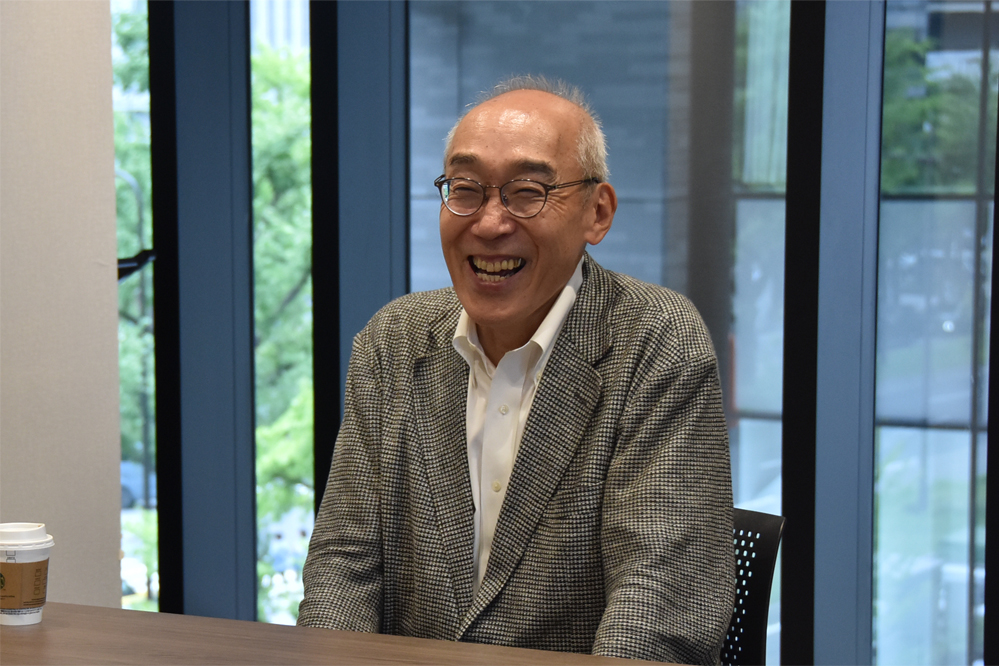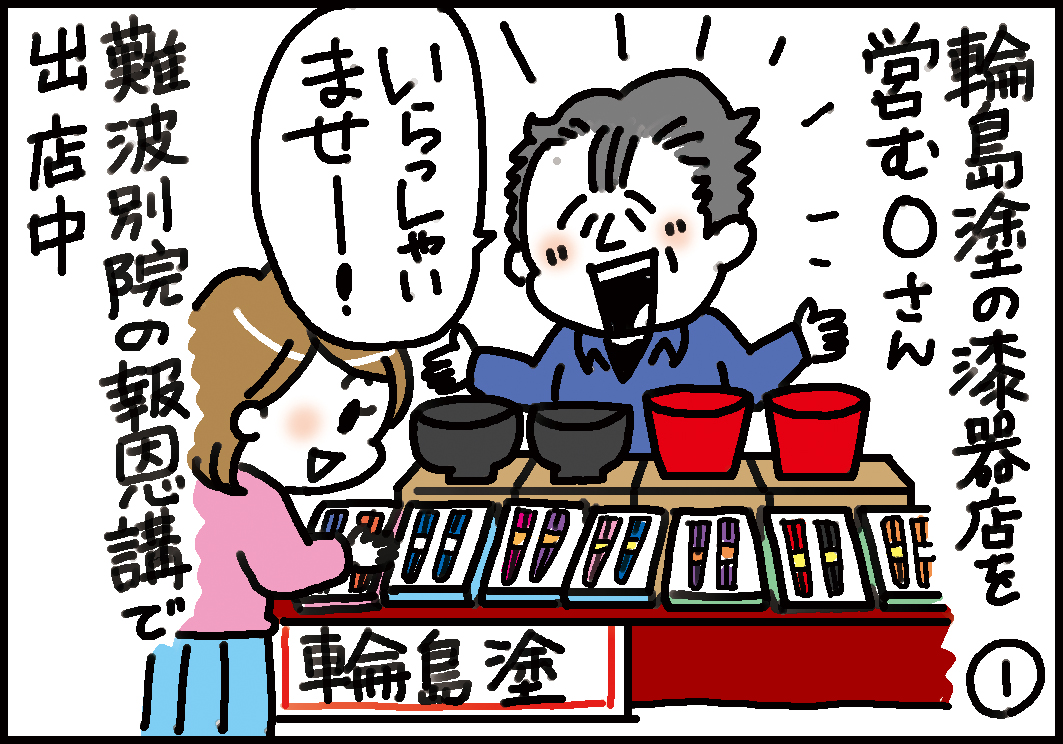高橋源一郎「私に届いた『歎異抄』」(前編)
ー傍らに立つ(上)ー

たかはし・げんいちろう
1951年広島県生まれ。作家、明治学院大学名誉教授。横浜国立大学経済学部中退。81年、『さようなら、ギャングたち』で群像新人長編小説賞優秀作となる。2012年『さよならクリストファー・ロビン』で谷崎潤一郎賞、ほか受賞多数。著書に、『一億三千万人のための「歎異抄」』(朝日新聞出版)ほか多数。
親鸞ひとりのため
阿弥陀が願をたて
いつ頃『歎異抄』を読むようになったのかは、はっきり覚えていない。まだ若者の頃だったと思う。それは「教養のために読むべき本」の一冊だった。読んだ。そして「なるほど」と思った。それから忘れた。たいていの本はそうだった。中には一節やストーリイを覚えている本もあった。登場人物に共感できる本もあった。そして本を読むことで自分は「豊か」になるのだと思った。みんながそう言っていたからだ。
あるとき突然、自分は本をきちんと読んでいないことに気づいた。なにもわかっていなかった。わかったふりをしているだけだった。印刷された文字を漫然と目で追っているだけだった。「わかる」ということは、そうではなかった。「読む」ということは。
なにか本を読んでいた。気がつくと、ぼくの横に作者がいた。いや、作者の横にぼくがいた。そんな気がした。どきどきした。なにか大切なことを作者は言おうとしていた。その現場に、いままさに立ち会っているのだ。作者がぼくをちらりと見たような気さえした。そしてこう言っているのだった。「いまからわたしのやることを見ていなさい」と。
『歎異抄』の後序にはこうある。
「聖人(親鸞)のつねのおおせには、『弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ』と御述懐そうらいしこと」(『真宗聖典』783頁〈初版640〉)。
ぼくはこう訳した。
「おれは考えに考えたあげく、ついにこう思うようになったんだ。アミダが永遠に近いほど長く考えられ、そして立てたあのお誓いは、ただおれひとりのためのものだったんじゃないかって。アミダは、こんなにもたくさんの罪にまみれたおれを救ってくださろうとあのお誓いをなさった。なんてありがたいことなんだろうって」
“読む”ことの本質
作者はそばにいる
なにかを読む。そこには、それを作った、それを書いた誰かがいる。「かつていた」のではない。「いまもそこにいる」のである。「いまもそこにいて」、それを読む、それを眺めているぼくたちの傍にいるのだ。そう、「その人」は、ぼくたちの「傍ら」にいるのである。あらゆる信仰、あらゆる創作、あらゆる表現。いや、それだけではない。ぼくたちの周りにあるものすべてが、「かつてどこかにいた誰か」が、「ぼく」たちひとりひとりのために作ったのではないだろうか。仮にその姿がいまはぼくたちの目に見えないとしても、その存在を感じることはできるのではないか。
『歎異抄』を開く。そこに、ぼくは「唯円」がいることを感じる。そして、その「唯円」の傍らに、「唯円」が憧れた「親鸞」がいることを感じる。それが「読む」ということなのだと思う。「彼ら」はいつも、ぼくたちの傍らに立っているのである。
【『南御堂』新聞2025.5月号掲載】