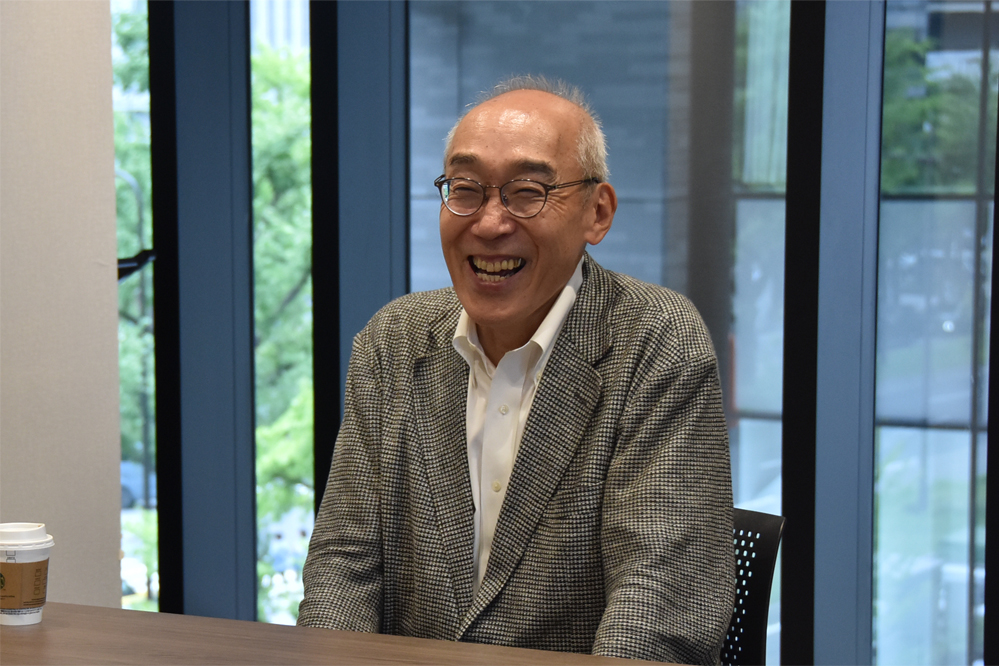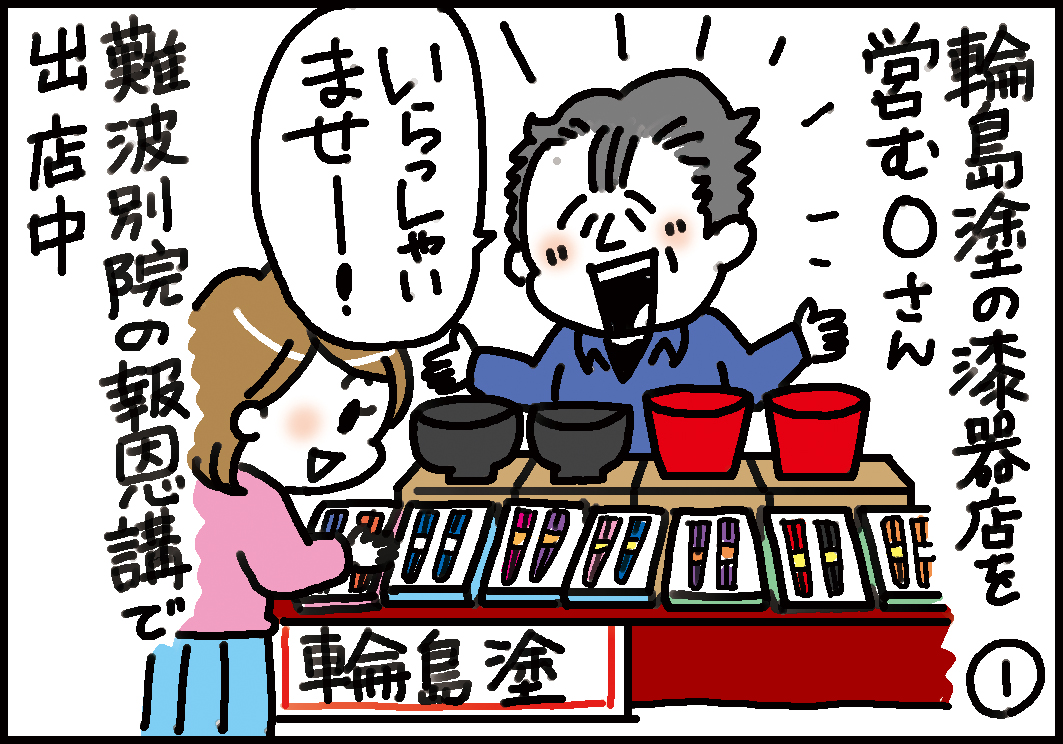難波教行「私に届いた『歎異抄』」(後編)
ー親鸞聖人御物語(下)ー
-1024x1024.jpg)
親鸞聖人亡き後、門弟の唯円が著したと伝わる『歎異抄』。そこには、唯円によって憶い起こされた親鸞聖人の言葉――「親鸞聖人御物語」が記されている。
物語と言うからには、一度聞いたら、もう聞かなくてよくなるというものではない。『歎異抄』は、繰り返し聞くべき物語を届ける書だったのだ――。
人間に必要なもの
あるとき、物語の力を語る天童荒太氏(作家)の言葉に出会った。「人間にとって究極的に必要なものが4つある。それは『衣』・『食』・『住』、そして『物語』だと」(月刊『同朋』2013年5月号)。
天童氏は、2001年にアメリカで起きた9・11の後、アフガニスタンへの報復攻撃が行われたことを悼み、そう述べた。人の命が奪われたことを悲しみ怒っているのに、それに対する行為がまた人を殺すことだった。そして多くのアメリカ国民や、日本を含めた先進国の政府が支持したのである。
天童氏は、次のようにも語った。「報復をするのが正しいと思ったのは、『やられたらやり返すのが正義』という物語がずっと彼らの中にあるからではないか。それに対して、『やられてもやり返さないことが正義』という物語がもっと浸透していれば、あんなに多くの人が報復を支持することはなかったのではないか」と。
もちろん、ここで『歎異抄』のことが直接語られているわけではない。しかし、物語には人間を育てる力がある、そう気づかせてくれた言葉だった。
物語の届け先
では、『歎異抄』は、親鸞聖人が物語った言葉を誰に届けようとした書なのだろうか。序には「偏に同心行者の不審を散ぜんが為」(『真宗聖典』767頁〈初版626〉)とあり、後序には「一室の行者のなかに、信心ことなることなからんために」(同785頁〈初版641〉)とある。つまり『歎異抄』は、浄土真宗の教えを広く世の中に向けて説明するために書かれたのではない。親鸞聖人の教えを聞き、念仏する人々に届けようとした書なのだ。
唯円が親鸞聖人の言葉を届けようとしたのは、そうした人々の中に「不審」や「信心ことなること」があったからである。ただし、歎かれているのは、教えが分からないことというよりも、むしろ、分かったつもりになって、自らの勝手な解釈を語っていることだと考えられる。
たとえば『歎異抄』第六章には、共に念仏の教えを聞く者の中で「わが弟子ひとの弟子」(同770頁〈初版628〉)と言って主張しあう状況に対し、「親鸞は弟子一人ももたず」(同)と述べた親鸞聖人の言葉が記されている。共なる地平を明らかにする念仏の教えに出会っても、なお、人の上に立とうとする人間の問題が示されていると言えよう。
そして他の章を見れば、こうした唯円の歎きは、他者に対するものにとどまらず、自らにも向けられているのである。
歎異のこころ
「不審」や「信心ことなること」があったからこそ憶い起こされた親鸞聖人の言葉が、『歎異抄』には記されている。ならば、異なることを歎き、幾度も教えを確かめてきた〝歎異のこころ〟が、「親鸞聖人御物語」を現代に届けてくれたと言わなければならない。
その物語に無数の先達が育てられてきた。はたして私はどうだろうか。『歎異抄』が著され、私に届いた歴史に想いをはせながら、今あらためて「親鸞聖人御物語」に耳を澄ませたい。
【『南御堂』新聞2025.10月号掲載】